福岡県地理全誌巻之三十九 (第五大区) 遠賀郡之一
(三十五小区四村之内)浅川(あさかわ)村
浅川村概説
(西南)福岡県庁道程十三里二十五町
彊域 東、本城村(二十三町余)。南、折尾村(二十八町余)・頃末村(一里十二町)。西、猪熊村(二十五町)。北、高須村(十町余)・小敷村(二十二町)・塩屋村(二十町)に接し、人家は、本村(山口・向《むかえ》三十四戸)、三頭《みつがしら》(十一戸、遠賀川・曲川・江川の三流会して海潮の遡る口なり。故に三頭と云う)。隠田《かくれた》(四戸)、龍谷《りゅうがたに》(一戸)、唐戸(一戸)、永谷(一戸)の六所にあり。村の名義は、此邊、古の洞海にて、大船も通いし所なるか。(今も土中を掘れば、貝殻多く出ず。これ海中なりし徴なり)。年を経て田地を墾開し村落をなし、今はわずかに潮水通うばかりの川となりて、此村の邊り殊に浅ければ、浅川と呼ぶなるべし。村位、中。地形、平低。運送の便、上(芦屋町一里)。土質、青沙真土に交じる。七分乾地、三分湿地。地味、下。田は中晩稲・麦、畑は麦・菜種・蕎麦等を作る。
戸口・田圃・租税・山林
○戸口
一 戸数 七十六戸
内
一 士族二十四戸
一 平民五十二戸
一 口数 三百七十三口
内
一 男 百九十四口
一 女 百七十九口
(職分)医術(男 一人)。農(男 七十四人、女 七十八人)。
雑業(男 二人、女一人)。雇人(男八人)
○田圃
一 田畑段別 四十町八段二畝十二歩五厘
此石高 三百三十八石八斗五升八合六勺
内
一 田段別 二十三町四段四畝三歩
此石高 三百八石一斗八升五合二勺
一 畑段別 六町五段一畝二十歩
此石高 三十石六斗七升三合四勺
一 大縄田畑段別 十町六段二十九歩五厘
○租税
一 米大豆 百六十石六斗三升三合 正租
此代金 四百三十八円九十七銭六厘
内
一 米 百五十石九斗六升五合
此代金 四百一円二厘
一 大豆 九石六斗六升八合
此代金 三十七円九十七銭四厘
一 米大豆 四石八斗一升九合 雜税
此代金 三円十六銭九厘
内
一 口米 四石五斗二升九合
此代金 十二円三銭
一 口大豆 二斗九升
此代金 一円十三銭九厘
一 金 一円七十七銭二厘
○山林
一 山段別 百五町五段四畝十五歩
内
一 五十一町歩 官林
一 四十五町一段一畝二十二分歩 草山・野山
一 五段歩 元拝領山
一 六町一段三畝十歩 元証文山
一 二町四段六畝三歩 元預山
一 三段三畝十歩 社山
橋梁・池塘・牛馬・車輪・山岳・河渠
○橋梁
一 石橋一所(中川筋本川内 官費) 長一間半 幅五尺
一 同 一所(同川筋戸口 同上) 長一間 幅四尺
一 同 一所(龍が谷川筋 蔵の前 同上) 長一間二尺 幅五尺
一 同 一所(同川筋洗石センセキ 同上) 長一間 幅五尺
一 (高須村催合)同一所(江川筋荒手同上) 長七間 幅六尺
○池塘
一 池八所
内
一 一所(永谷 官費) 水面二町歩 水掛田九町四反六畝歩
一 一所(龍が谷 同上) 水面八反歩 水掛田七町八反歩
一 一所(金丸 同上) 水面一反二畝歩 水掛田六段三畝歩
一 一所(大海田オオミタ 同上) 水面一段三畝歩 水掛田六反五畝歩
一 一所(薦 同上) 水面一反三畝歩 水掛田一町歩
一 一所(後海田 同上) 水面四反五畝歩 水掛田九反五畝歩
一 一所(苗が谷 同上) 水面五畝歩 水掛田五反五畝歩
一 一所(丸畠マルバタケ 同上) 水面三畝歩 水掛田五畝歩
以上築立年不詳
○牛馬
一 牛 二十七頭
内
一 牡 二 頭
一 牝 二十五 頭
一 馬 十三 頭
牡 三 頭
牝 十 頭
○車輪
一 人力車 四輌
○山岳
日峯山 ヒノミネヤマ
村の西南にあり(火の峯とも書けり)。山麓、鋤坂より絶頂へ十二町。険阻。松・小竹立つなり。
○ 河渠
江川
東北、小敷村界より流れ来たり、村の北を過ぎて曲川に合流し遠賀川に入る。長八百七十間。幅平均六間。平潮一尺五寸。満潮四尺。石刎橋一所(荒手、高須村催合)。仮板橋一所(荒手)
曲川
南、猪熊村界より流れ来たり、村の西を過ぎて江川に入る。長七百五間。幅平均八間半。平潮三尺。満潮四尺。唐戸一所(三ツ頭・猪熊村催合。長八間幅二間)
岩石・神社(日峯)・仏寺・古蹟・墳墓
○岩石

上﨟石
日峯の八分ばかりにあり。高一丈余。婦人の姿に似たるを以て名づく。また琵琶石とて焼火神、この山に降臨ありて琵琶を弾じたまいしと言い伝えたる。石、近世までありしが、今はなし。

○ 神社
(村社)日峯神社(上宮、石祠一間四面。下宮、本殿一間半四面。渡殿横一間半入二間。拝殿横四間入三間。石鳥居・木鳥居各一基。社地三千坪。氏子四十八戸)
上宮は日峯の絶頂にあり。下宮は村の西五町余にあり。祭神は比奈麻知比売命・天照大神・彦火火出見尊。祭日は九月十八日。
社説に清和天皇貞観二年庚辰四月十九日、烏珂真彦と云う者に神託あり。云く、「この山に隠岐国比奈麻知咩の神、来現したまう。故に社を立て祭れり」と。舟、洋中往来、舩は暗夜に津を失う時、この神に祈れば必ず神火顕るる事あり。古今、奇異の霊験なり。『香月家記』に「小碓尊、大和に登り而して筑紫国に航り遠賀湊に到らんと欲するの日、海潮湧き起ち、逆風にして急雨、日すでに暮れる。檣(ほばしら)は傾き梶は砕く。御船、将に顛倒せんとす。尊(みこと)、天神地祇に祈り布を給う。筑紫に在りし火神、不知火を出して天に給す。光輝赫々、海面白日に異ならず。又、西の峰に大聲喚起する有り。曰く「御船を此方に寄せよ云々」。舟子、その聲に従い、而して御船を西津に寄す。即ち今の大渡川(※洞海湾のこと)、是なり。その西方は即ち今の於比羅比山、是なり。後に火神、遠賀郡嶋郷に跡を垂れ、近世、火焼権現と称するは是なり」とあり。
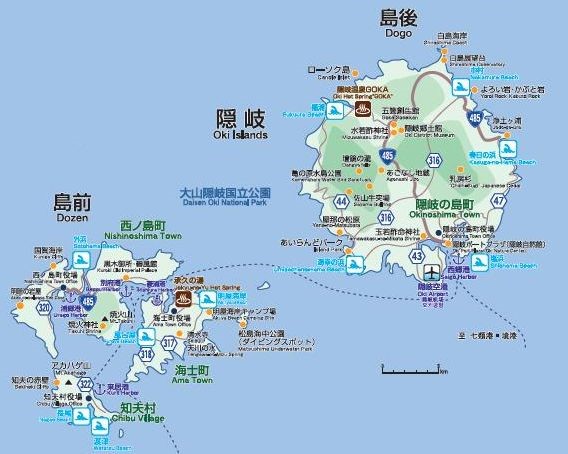
延喜式神名帳に隠岐国知夫郡比奈麻知比売命神社、又由良比売神社(名神大、元名、和多須神)と見えたり(加藤一純云わく「別本前代旧事本紀にはこの神を在沖城玲瓏宮立燈守舩大神」とあり。又、或る説に「一条院の御宇は大山権現と云いし」と云えり。今、按ずるに平田篤胤が古史伝に「隠岐国知夫郡海神社に座す」とあり。この社に並びて同郡に由良比女神社名神大元名和多須神と申す社あり。此は承和九年九月官社に預かりたまう由、国史に見ゆ。和名抄に「由良郡あるは、此の神の鎮座す所なるべし」と云い、由良比女神社の下に元名和多須神とある六字は、海神社二座の下にあるべき由、或る人の説を載せたり。
宮永保親が説には、「この社は菟夫羅媛(※ツブラヒメ岡湊の祭神)を祭れる社にて、菟夫羅媛は即ち由良媛、由良媛は即ち須世理媛(※スセリヒメ素戔嗚尊の娘、大国主の正妻)の一名なり」と云う。詳らかに高倉村神社の條に載す。又、その説に神名の由良は円なる物の動く音を云う。古事記に「その御頸珠(※ミクビタマ)の玉の緒も由良に取りゆらかして云々」と見え、又、書紀に「玲瓏」を「ゆらぐ」ともよめり。これ、この言の出たる証なり。都夫良(※ツブラ)は円なるを云う。
古事記上巻「その海水の都夫多都(※ツブタツ)時の名理を都夫多都御魂」。又、履中紀に「円大使主(※ツブラオウミ)、国事を執る(円はこれ都夫羅と云う)」とあり。されば都夫良は円なる物を云う。由良はその物の音なりを云う詞なり。かくて都夫良媛の由良媛なる事を知るべきなり。又、郡名の知夫は古事記十六巻に「物の水に没入沈むを、つぶりと入る云うとあるが如し。「つぶり・ちぶり・つぶら」は同言なれば、是も彼神の証とするに足れりと云うは、さもあるべし。されども古史伝(※平田篤胤の注釈書)は、海神を由良姫神とする説なれば、保親が説とは異なり、神火の霊験あるは比奈麻治比売神なる事、日本後紀の文に明白なれども、由良姫も同じ神徳おわせるにや。須世理姫を菟夫羅姫と同神とすれば、湊に入る船を司りたまう神にて、仲哀紀の「浦口ある神云々」とあるも考え合わすべきなり)
日本後紀桓武天皇紀延暦十八年五月丙辰、前遣渤海使外従五位下内蔵宿祢賀茂麻呂等の帰郷の日、海中の夜は暗く、東西に掣曳され、著く所を識らず、時に遠く火光あり。その光を尋ね逐い、忽ち嶋濱に到る。之を訪ぬれば、是、隠岐国智夫郡なり。そこは人居有る無し。或いは云う、「比奈麻治比売神、常に霊験あり。商賈の輩、海中に漂宕すれば必ず火光揚がる。之を頼りて全きを得る者、数うるにたうべからず。神の祐助、良しく喜ぶべき報せにして、伏して望み弊を預け奉る例なり。之を許するは、その後の歴史にもこの御神の事、往々出たり。

承久三年、後鳥羽院、隠岐国に遷幸したまう時、海上の風波烈しく、御船も危うかりしかば、御製
我こそは新島守よ おきの海のあらき波風 こころして吹け
夜に入りて風猶烈しく、御船を寄すべき方も見えざるに、神社のまします所より、火を立てたまうにより、風波の難を逃れ着岸したまう。此の時の御詠に
灘ならば藻塩やく家と思うべし なにを焼火の烟りなるらん
初め院、「何を焼間」と遊ばされしを、「焼火(※タクヒ)」にすべしと神託ありしとなん(隠岐国知夫郡焼火山縁起に見ゆ。同社宮司の坊を焼間山雲上寺と号す。縁起は天和三年、住僧快順撰するところなり)当社の外、国中に焼火神社多し。皆、同神なり。
(※日峯神社の)下宮に永正十六年(※1519)己卯、社檀再興の棟札あり。
摂社三 菅原神社(三ツ頭。宝永年中、村民に霊告ありて神体を得たり。同じて社を立つ)。大山祇神社(同上)。須賀神社(同上。神木の松あり。昔は社はなかりしが、宝暦中、疫疾流行せし時、この神木に祈願して病患を免る。故に社を立て祭る)。
末社三 菅原神社。市杵島姫神社。貴船神社(共に社地)
※「摂社」は主祭神と関係の深い神様を祀っている場合。 「末社」とは主祭神とはあまり関係のない、客分の神様を祀っている場合とおおよそ区別されているようです。
○仏寺
小堂二所
観音堂(本村の内、寺山にあり。阿弥陀同堂に五百羅漢ありしと云う。その遺像十躯ばかり猶存せり)。大師堂(同上)。
○古蹟
陣山城址
村の西二十町にあり。麻生氏の端城なり。山上、松樹茂り、荊棘蔓りて、地形広狭尋ねがたし。
○墳墓
三好某墓
本村の北一町、時里にあり。高三尺五寸ばかり。野石に法名良照院湛譽秋覚、慶長七年八月二十五日と銘せり。此村を墾開せし、三好某の墓と云う(今も村中にこの氏の者多し)。
附記(物産)
○附記
物産
一 米 五百六十九石九斗一合 生出
一 麦 五十石
一 小麦 二石
一 大豆 十五石九斗五升
一 小豆 一石五斗
一 豌豆 三石
一 唐豆 二石五斗
一 蕎麦 十二石五斗
一 柿 八千五百
一 綿 十二貫目
一 鶏 九十羽
一 鶏卵 三千五百
一 鶏卵 二千 輸出
此代金 十円
一 櫨実 六百二十斤
此代金 七円四十四銭
一 薪 四万斤
此代金 二十円
総計 金 三十七円四十四銭



コメント