福岡県地理全誌巻之三十九 (第五大区) 遠賀郡之一
(二十五小区二村之内)前田(まえだ)村
1.前田村概説
(西南)福岡県庁道程十六里十八町
彊域 東、尾倉村【十五町】。西、藤田村【十六町余】。北、内海【四町】。東北、大蔵村【三十五町】に接し、人家は、本村【七十二戸】、和井田【十八戸】、臺良ダイラ【二戸】、祇園原【六戸】、四所にあり。慶長の頃までは、藤田村の内なり。寛政年中、和井田の北二町余に石垣、東西長四百二十間余、幅二間半を築きて五町六反七畝歩の新田を開けり。村位、下。地形、南高くして北低し。運送の便、上【黒崎駅官道、本村】。土質、東西沙青土、南北小石赤土交じり。乾湿相半す。地味、下。田は中稲・麦・菜種。畑は菜種・麦等を作る。旱損の患いあり。土産、白藻(シラモ ※寒天の材料)
2.戸口・田圃・租税・山林
○戸口
一 戸数 百三十四戸
内
一 士族八戸
一 平民百二十六戸
一 口数 六百三十四口
内
一 男 三百十九口
一 女 三百十五口
【職分】筆学【男 一人】。農【男 百七十五人、女 百六十三人】。
工【男 十人】。雑業【男 十五人、女 十四人】。雇人【男 四人、女 三人】
○田圃
一 田畑段別 六十八町五段五畝歩
此石高 五百十一石七斗三合二勺
内
一 田段別 四十六町一段九畝五歩五厘
此石高 四百四十七石五斗七升四合五勺
一 畑段別 十四町五段三畝十六歩五厘
此石高 六十四石一斗二升八合七厘
一 大縄田畑段別 七町八段二畝八歩
○租税
一 米大豆 二百四十八石一斗七升三合 正租
此代金 五百九十五円二十四銭四厘
内
一 米 二百十四石九升一合
此代金 五百九十五円二十四銭四厘
一 大豆 二十四石八升二合
此代金 九十四円五十八銭九厘
一 米大豆 七石四斗四升五合 雜税
此代金 二十円六十九銭四厘
内
一 口米 六石七斗二升三合
此代金 十七円八十五銭八厘
一 口大豆 七斗二升二合
此代金 二円八十三銭六厘
一 金 二円八十銭二厘
○山林
一 山段別 六十八町八段二畝九歩
内
一 十六町四反八畝 官林
一 四十七町歩 草山
一 四町二段二畝一歩 古野建出山
一 一町一段二畝八歩 社山
3.橋梁・池塘・牛馬・学校・電線
○橋梁
一 橋 五所
内
一 石橋一所【小伊藤川筋小伊藤 官費】 長一間一尺五寸 幅一間五尺二寸
一 同 一所【犬付川筋犬付 同上】 長一間 幅一間五尺二寸
一 同 一所【溝川筋瀬戸原 同上】 長一間 幅一間四尺五寸
一 同 一所【同川筋一里塚 同上】 長二間一尺五寸 幅二間
一 土橋一所【祇園原川筋平野 同上】 長二間 幅一間半
一 同 一所【東田川筋射場の本 民費】 長二間三尺二寸 幅二間
○池塘
一 池 四所
内
一 一所(和井田 官費) 水面四反歩 水掛田二町一反歩
明和六年己丑築立
一 一所(野添 同上) 水面一反六畝歩 水掛田一町五反歩
寛政八年(1631)丙辰築立
一 一所(犬付 同上) 水面五反歩 水掛田三町八畝歩
文久三年(1863)癸亥築立
一 一所(山神 同上) 水面一町二段歩 水掛田二十八町五反三畝歩
築立年不詳
○牛馬
一 牛 六十二頭
内
一 牡 三十三 頭
一 牝 二十九 頭
一 馬 十八 頭
牡
○学校
一 小学校【祇園原】
生徒二十七人
男
〇電線
一 機柱 十八本【三百六十三号より三百八十号に至る】
東尾倉村界より西藤田村界に通ず。道程八町五十五間
4.山岳・神社・仏寺・古蹟・墳墓
〇山岳

皿倉山
村の東南にあり。山麓祇園原より絶頂へ二十五町、雑木立。険阻なり。峰続きに帆柱山あり。杉木多し。
花ノ尾山
村の南にあり。山麓祇園原より絶頂へ十八町。険阻。小篠立なり。


坊住山
村の西南にあり。山麓祇園原より絶頂へ一里。険阻。杉立なり。
※ 距離と方向から現在の権現山と思われる。
〇神社
仲宿八幡宮
【村社】八幡宮【本殿 横一間半四面。渡殿 二間四面。拝殿 横三間入二間。石鳥居一基。社地三百坪。氏子百三十二戸】
本村の内、中宿ナカヤドリにあり。祭神は品陀別命ホムタワケノミコト(応神天皇)・帯仲津日子命タラシナカツヒコノミコト(日本武尊の第二子)・息長比賣命オキナガヒメノミコト(神功皇后)。祭日は八月二十四日。
慶安元年(1648)戊子八月、尾倉村八幡宮を迎え祭れり。この地名は往昔、神功皇后ここに舎らせたまいて中宿りと詔いしより起これりと云えり【今、里民は訛りて中あたりと云う】。

社前に石の盥盤(ちょうずばち)あり【この村の内、皿倉山の麓、石場という所より東叡山に寄送の鳥居石を伐り出す。その額石いかなる故にか、海邊に棄て船に積まざりしかありしを、宝永四年(1707)、村民等社地に運び取りて盥盤とすと云う】。
摂社 四。
八束髪ヤツカカミ神社【祇園原にあり。前田村祇園社の古址なり。馬場の左右を今市と云う。当社繁栄の時、市立ちし地なり】。 貴船神社【中宿。村の東に貴船田あり】。龍宮神社【下邊】。芦原神社【和井田】。
※ 写真は八束髪神社

末社 三。八幡古宮【貴船田】。稲荷神社【和井田】。高見三所神社【高見山の西の嶺に大石あり。是を祭りて高皇産霊尊タカミムスビノミコトと称す。社は無.し。その初め神功皇后、祭りたまいし由言い伝う。麻生氏、帆柱山に在城の時、白山神を合わせ祭りしより、高見白山と称す】。
小社 三所

孕石ハラミイシ神社【祇園原八束髪神社の北に雑木立の森あり。中に一箇の石立てり。高四尺五寸。周二尺九寸。その状、胎孕の婦人の立てるが如し。故に孕石の名あり。神と崇めり。皇后石とも云う】。
山神社【山神】。権現社【中村】。
〇仏寺
小堂 三所
地蔵堂【隠作カクレツクリ】。観音堂【宮ノ馬場】。
〇古蹟
源経基陣址
村の西九町、藤田村界、官道の側に、陣山という地あり。古松一株立てり。
昔、藤原純友征伐の時、六孫王経基の陣所なりし由、村民言い伝えり。
尾倉八幡宮址
村の東三町、貴船田といえる所の田圃中にあり。礎石あり。本社の跡、八間四面ばかり。拝殿跡を瓦田という。今も布紋の古瓦出ず。また、門田・神田・錫田・味噌田・五月田・御供田・三反田等の字あり。
御屋敷
中宿八幡宮の側にあり。前田氏の宅址という。詳らかなること知れず。
〇墳墓
経塚
本村の内、中村の林中にあり。大杉の下に五輪塔あり。里民、花尾城主姫君の墓と云う。側に五輪塔の崩れたる多し。
古墳 二所
村の東北三町、小森という所の圃中にあり。この邉二十間ばかりの所に、古墳大小三十二あり。里民は、麻生氏累代の墓とも加賀塚とも云う【按ずるに、これは前田というによりて、加賀国主に附会せるものなるべし。麻生氏の墓というを実とすべし】。この塚、祟厲(激しい祟り)をなして、里人悩めること度々ありしより、近年ここに社を立て、龍神と崇む。又、この邉の田間に海桐トベラの木生えたる小塚あり。姫の墓と云う。よりて、この塚を海桐の森と呼べり。
5.附記(物産)
一 米 七百六石六斗 生出
一 麦 四百石
一 大豆 二石
一 小豆 二石一斗
一 豌豆 二石八斗
一 唐豆 二石
一 蕎麦 四石二斗
一 里芋 一石一斗
一 大根 二千五百本
一 鶏 七十五羽
一 鶏卵 三千
一 綿 五十六貫目
一 茶 一貫百目
一 麦 六十石 輸出
此代金 百二十円
一 山芋 三百本
此代金 一円八十銭
一 白藻 七十斤
此代金 五円六十銭
一 鶏卵 千九百
此代金 九円
一 菜種 九石五斗
此代金 五十八円四十二銭
一 櫨実 一万二千八百斤
此代金 百五十三円六十銭
総計 金 三百四十八円四十二銭
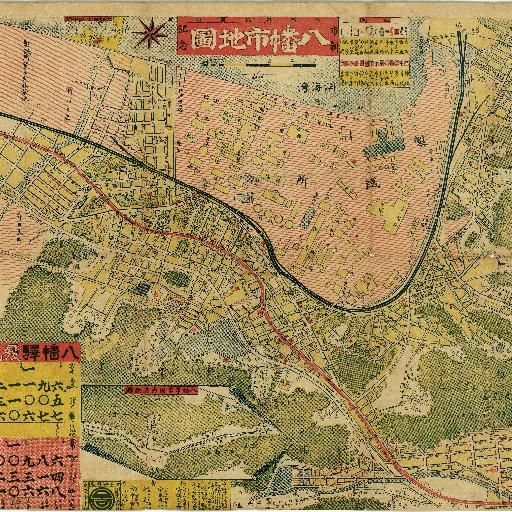


コメント