【はじめに】
令和5年3月、宮若市文化振興シンポジウムで、質問タイムに小金原合戦を「小競り合い」と失言し、敬愛するN先生を激怒させてしまいました。
その夜、「たとえ質問といえども、生半可な理解でしちゃいけない」と反省し、自罰として「続風土記」の小金原合戦についての記事と桑田和明先生の資料を現代語訳することにしました。
本来なら、考察や地図なども付けるべきなのですが、秋月氏の動態など、まだ勉強が終わっておりませんので、とりあえず現代語訳だけをUPします。
N先生、本当に申し訳ございませんでした。
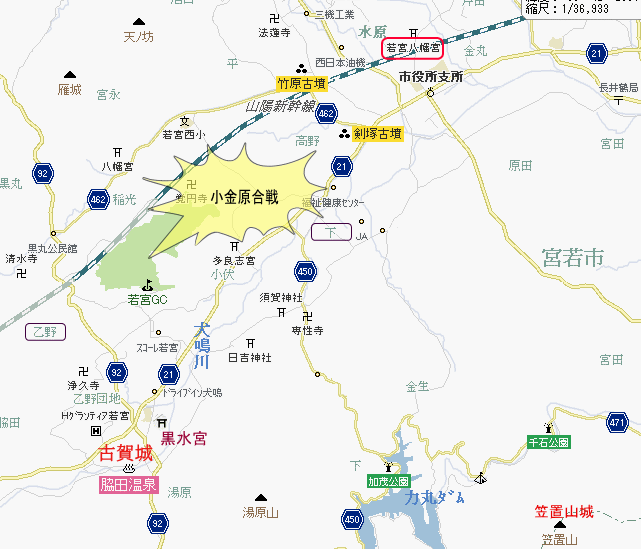
- 1.『筑前国続風土記』巻之二十六古城古戦場三「小金原」の現代語訳
- 【西郷衆について】
- 【宗像氏と立花城衆の対戦】
- 【立花氏と宗像氏の和睦と婚姻、西郷衆の遺恨】
- 【戸次道雪が、鷹取城の毛利種(鎮)実に兵粮を送る】
- 【龍徳城の杉連並が、立花衆を攻めて反撃される】
- 【若宮衆(旧西郷衆他)の軍議】
- 【立花勢が、友池川を越え、河津修理進を鉄砲で打ち倒す】
- 【友池・金丸衆が、立花勢を攻めて優勢】
- 【薦野・米多比が反撃、河津・深川を打ち破り、稲光の城山に登る】
- 【近隣の宗像衆・笠木城の秋月衆が、小金原に出陣する】
- 【宗像氏貞が、停戦のため吉田・石松を遣わす】
- 【吉田・石松は、若宮衆を説得できず、合力を約して戦いに加わる】
- 【若宮・石松・秋月の800人,稲光の城山を攻めんとし反撃される】
- 【宗像勢敗北、吉田・石松・若宮の士150~160が討死】
- 【翌朝、立花衆が、山越えに引き取る】
- 【当時人々の評価】
- 【宗像氏貞が千余人で出陣するも、敗戦を知り引き返す】
- 【貝原益軒の評価】
- 2.古文書から見た「小金原合戦」の書き下しと大意(桑田和明-令和5年3月18日、宮若市文化振興シンポジウム冊子から)
1.『筑前国続風土記』巻之二十六古城古戦場三「小金原」の現代語訳
【 】の項目、※、( )の註記は河島がつけました。
【西郷衆について】
小伏、高野、稲光、三村の境に長い原がある。小金原という。若宮河内と吉川河内との間にある。またその辺には小金原という小村がある。枝村である。槍場というところが小伏の境内にある。この所は、※天正10年(1582)11月13日、立花、宗像両家氏の戦場である。その合戦の始終を調べてみると、宗像郡西郷の庄に、川(河)津民部・深川修理・温科将監・井原左衛門入道・難波将監・桑原雅楽助・河野弾正・石津などという士がいた。昔は立花家にも従わず、また、宗像氏にも与する様子はなかったが、永禄10年10月に、過半が宗像旗下となった。(宗像)氏貞も内々では彼らを旗下にしようとしていたので、大いに喜んで、川津・深川を頭とし、その他36人の与力をつけ、立花への押さえとして、そのまま西郷に差し置いていた。
※ 小金原合戦の期日は、天正9年説と10年説があるが、最近は9年説が有力である。
【宗像氏と立花城衆の対戦】
立花鑑載・怒留湯融泉は、彼らを攻め随えようとして、薦野河内・同弥十郎・米多比大学らを先手として千五百余人が、西郷・福間辺りに出動し、下府村に陣を取った。宗像氏貞はこれを聞いて、赤間の城を出、許斐左馬大夫・占部越後・大和治部らを先手として、二千余人が福間河原へ押し出し、川を前に当てて陣を取った。しかし、双方弓鉄砲でのせり合いばかりで4,5日が過ぎるところに、秋月・宝満(高橋鑑種)の両城が強くて落ちず、かつ両城の後詰めとして、中国勢(毛利)が来るという情報が入ったので、鑑載・融泉は、立花表が心許ないと、薦野河内・同弥十郎を後殿として、夜中に軍を引き上げた。 宗像勢もさほど追い打ちをかけなかったので、落ち着いて立花・薦野は城に各々入った。
【立花氏と宗像氏の和睦と婚姻、西郷衆の遺恨】
その後立花・宗像の両家は和睦し、領地の境を確定することとし、後々まで異変がないようにと、婚姻を結び、氏貞の妹おいろ姫、今年24歳を立花鑑連(道雪)に嫁せしめた。化粧田として西郷の庄を鑑連に送った。また、鞍手郡若宮郷は、元来宗像領であったが、近年立花方に切り取られていたのを、この度、宗像に返した。これにより若宮郷は宗像の領地となり、西郷は立花の領地となって双方分かれたので、川津・深川をはじめ郷士・与力たちの屋敷領地を、鑑連から小野・十時・堀・安東・内田などの士に賜ったので、新給人たちは馳せ回って西郷衆を追い立てた。川津・深川は腹を立てたが、憤りを抑え、今回の替地として氏貞から賜った若宮河内・長井鶴に家を作って移り住んだ。
しかし、民部・修理以下は、住み慣れた西郷の家を、何の抵抗もできずに追い立てられたことを無念におもい、「何事か起こってくれ。そうしたら立花家の家人と差し違えて死に、悪霊となって鑑連にこの恨みを晴らすぞ」と時節を待ち、怒りを抑えて年月を送っていたとは筆舌に尽くせぬことであった。
【戸次道雪が、鷹取城の毛利種(鎮)実に兵粮を送る】
このようなところに、鞍手郡鷹取城主毛利兵部少輔種(鎮)実、大友方で無二の忠を尽くしていた者が、最近は大友家からの加勢もなく、秋月・杉らに領地を悉く掠め取られ、城中の兵粮もすでにつき、餓死する者も出ているとの情報が立花に入った。鑑連・統虎は家臣を集めて評議し、「今は諸方に敵が多く、遠方を助けることは難しい時期ではあるが、味方を捨て殺しにすることは大友家に対して良いことはなく不忠というものである」と、兵粮を送ることを決定したが、「若宮の庄に西郷から移った36人の給人は、常々遺恨を差し挟んでいるので、運搬を妨げることもあるだろう」と、口々に鑑連に申し上げたので、「なるほど、たしかにそうだ」と、まず使者を派遣して宗像氏貞に「鷹取に玉薬兵糧を送って合力致すべく、御領分の若宮郷を往来致しますので、人数を通過させていただきたい」と申し送ると、氏貞から了承との返答があり、同時に若宮の(宗像)家人らに触れて「立花勢が若宮郷を通過するときは、粗忽の振る舞いがあってはならぬ」と厳しく命令を下された。しかしながら鑑連方は猶も用心のために、薦野三河・小野和泉をはじめ人数八百余人を指副奉行として、兵粮三百俵を人馬に負わせ、天正10年(1582)10月12日、鷹取の城に送った。
【龍徳城の杉連並が、立花衆を攻めて反撃される】
このような状況の中で、龍徳城主杉十郎連並の三百余人が道を遮って妨害したので、先陣に進んだ薦野三河・米多比五郎次郞の三百余人が喚声を上げて突きかかり、杉勢を散々に追い崩し、難なく兵粮を鷹取の城に届けた。
【若宮衆(旧西郷衆他)の軍議】
宗像の士で若宮郷にいた者の中でも、深川右京進貞国・河野伊豆守・井原次郞左衛門・原九郎貞永・鮎川六郎・古野甚九郎ほか諸々が加わり、合計51人が一味して言うには、「氏貞からの命令ではあるが、立花勢を安穏に通したことの無念さよ。我らは数代西郷の住人であったのに、西郷を何の理由もなく立花領とされ、住所を追い立てられ、その鬱憤はやるかたない。せめてこの者どもを討ち取って数年の遺恨を散じよう」と計画を練った。 人々が寄り集まって評議した結果、「若宮川をせき止めて水をたたえ、これを渡ろうとするところを弓鉄砲を打ち掛け、乱れたところを討つのはどうだ」との意見が出たので、「それが最善である」ということになり、河津修理進盛永を奉行として、杭を打たせ用意をした。
【立花勢が、友池川を越え、河津修理進を鉄砲で打ち倒す】
13日の午の刻(十二時頃)、立花勢は鷹取城を出て帰ろうとし、友池川まで来て(友池は金丸の下、長井鶴の上である)、小野和泉・由布雪荷が一番に川を越えたが、「昨日まで浅かった川が、雨も降らないのに増水するとは怪しい。敵の手立てではなかろうかと、四方に目を配りつつなおも行くと、河津が士卒に下知をしているのを見て、「不届きな怪しい奴、あいつを先ず軍神の血祭りにせよ」と、由布七右衛門が鉄砲で打ち倒した。
【友池・金丸衆が、立花勢を攻めて優勢】
これを見て友池の者どもが、われ劣らじと馳せ向かう。金丸の輩も聞きつけて馳せ出す。立花勢はひたひたと馬より下り、槍を揃えて敵を突き崩し原田を指して退くところを、友池金丸の者どもが後を付けてきたので、立花勢は人数を交互に車引きに引いていくのを、宗像氏の家人らは、あちこちから蜂のように集まり、蟻のように群れて戦ったので、さすがの立花勢も負け色になり、足立飛騨をはじめ数人が戦死し、由布美作をはじめとして手負いも多かった。
【薦野・米多比が反撃、河津・深川を打ち破り、稲光の城山に登る】
(立花勢で)二番にやってきた薦野三河・同弥助・米多比五郎次郞ら三百余人は、道を少し左に回り、鯨波(とき)を作って懸かったので、河津・深川は散々に乱れて引き退いた。立花方は追いかけて数多く討ち取った。(薦野)三河は深川五郎を討ち取った。米多比五郎次郞はそのころ17歳だったが、原孫九郎を討って名をあげた。かくて、立花勢は金生の前の川を渡り、高野をさして引いていたが、若宮所々の住人が遅れ馳せに駆けつけると、あるいは追い払い、あるいは討ち取り、少しずつ引いて稲光の城山に取り上り、士卒をまとめて兵粮を使い、人馬の息を休めた。
若宮勢も小伏の前まで追いかけ、ここで人馬を休めた。
【近隣の宗像衆・笠木城の秋月衆が、小金原に出陣する】
かくて近辺の城主は各々このことを聞いて、我も我もと氏貞の下知を待たず出陣した。秋月家臣江利内蔵助は穂波郡笠木の城を守っていたが、このことを聞くと同じく乗手石見・柏井九郎右衛門をはじめ三百余人を率い小金原に押し出した。
【宗像氏貞が、停戦のため吉田・石松を遣わす】
そしてこの戦さのことは岳山にも注進されたので、氏貞は驚き、吉田次郞左衛門貞辰・石松加賀守秀兼に「急ぎ馳せ向かい止めよ」と命ぜられたので、二人は馬を早めて馳せ向かうところに、吉田少輔六郎貞永・石松新三郎・同十郎らがこれを聞いて押っ取り刀で駆け出てきた。吉田飛騨も駆け出す。かくて吉田・石松は馬を早めていくところに、(西郷衆が)友池の戦いに破れ、高野を指して敵が引き取ったと聞いたので、「それではそこに向かって戦さを止めさせよう」と思い、原田・金生を打ち過ぎ、下村の川を渡り小金原に打ち出す。
【吉田・石松は、若宮衆を説得できず、合力を約して戦いに加わる】
友池・金生の人々は、小伏の前の野に馳せ集まり、馬を休め軍の評議をするところに、吉田・石松が馳せ着き、諸士に向かって言うには「これは如何なることを仕出かされたことか。氏貞様は以ての外の不機嫌で、我ら二人に仰せつけられ、急ぎ引き取れとの命でござる。早々に引き取られよ」と散々に叱りつけたので、皆が申すには「仰せもっともではございますが、このようになってはすぐに逃げて帰ることもできますまい。よしよし、氏貞様の御勘気を蒙ろうとも、我々が生きて帰ればご迷惑となるだろう。どうせ死ぬ命なのだから、あれこれ命令する必要はない。御辺たちは早々に帰って、このことを申し上げてくだされ」とかえって聞こうとしない。貞辰・秀兼は力及ばず、「それでは各々がそのように思い定めておられるならば、是非を論ずることもできますまい。このような御使いが参るのは時節到来の時には不祥であろうと、見捨てて帰るわけではない。さらば合力致しともに戦死いたそう」と各々は一手に加わった。
【若宮・石松・秋月の800人,稲光の城山を攻めんとし反撃される】
というわけで、金丸・長井鶴・その他若宮の郷のあらゆる士・雑兵あわせて三百余人、また赤間から馳せ来たる輩が石松十郎を筆頭に百余人、秋月勢と一つになって都合八百余人が、小伏の前に備えを立て、城山の敵にかからんとする。立花方の士どもは、今朝の戦さに人馬が疲れている。今、敵は多勢だと、少し嫌気が差して見えるところに、薦野三河が申すには、「各々方は、最初の戦さに全力を尽くされた。今度はそれがしにお任せくだされ」と、弥助成家・米多比五郎次郞を左右に備えて、三百余人が宗像勢に馳せ向かい、入り乱れて戦った。日は、はや申の刻(午後四時)になったので、石松が申すには「この夕日に向かって敵にかかろうとするのは、戦さの定法ではない。西に下りて備えを立て替え、北に向かって攻めかかれ」と下知するところに、立花勢はすでに城の高みから降ろし懸かる。友池勢これを見て「敵ははや懸かるぞ」といい、相懸かりに押し出す。立花勢三百余人は、高みより漲り落ちる滝の如く機に乗じて押しおろせば、受け太刀になった友池勢はどうして堪えることができよう、たちまち小伏の谷に追い落とされる。だが、再び谷より盛り返し切り上ると、夕日が眼の光を奪って、太刀の打ち所を定めがたく、面を挙げることもできない。立花勢は夕日を背負って攻め下る勢いだから、その鋒に当たることができるものではない。しかし、宗像勢は多勢で、特に若宮の者どもは必死を極めた兵士だから、立花勢と入り乱れ、もみ合い、再び押し上って戦う。互いに勝敗は不明であった。
【宗像勢敗北、吉田・石松・若宮の士150~160が討死】
そのようなときに、立花勢の中から内田壱岐入道玄恕が馬を乗り回し采を振って「先手が進まず戦いに負けるならば味方は危うくなるだろう。もうひともみせよ。」と下知した。それで小野和泉・立花中務・同越中・同右衛門大夫を先として三百余人が喚いて駆け入り、火が出るほどに戦ったので、宗像勢は遂に敗北した。吉田左近は深手を負って、戦さ半ばに手勢を引き連れ東を指して引き退いた。吉田貞辰・石松秀兼も討たれた。吉田少輔六郎は小伏において立花勢を追い返し、勇んでいるところに貞辰の馬添えの男が来たり合い、「貞辰様は討たれさせ給う」と申したので、少輔六郎はそれを聞いて、「兄を討たせて今はのがれぬ所である」と馬を引き返し、当の敵を討とうと大勢の中に切り入った。立花の大勢が待ち受けた中にただ一人駆け入ったので、取り包んで打ちとった。
石松十郎も父秀兼の討死を聞いて、これも馬を返し戦い討死した。若宮の士、百五,六十人は残らず討たれたが立花方でも名のある士三十余人が討たれた。日もすでに暮れたので、立花勢は「長追いはするまい」と清水に馳せ上って人馬を休め、兵粮を使い、観音堂に入って一夜を明かした。討ち取った首は堂の前に並べ置いた。
【翌朝、立花衆が、山越えに引き取る】
明ければ14日の早天に山越しに引き取ったが、かの険しき鉾のたをを乗り越え、清瀧のがけ地を乗り落とし、薦野を指して帰った。(石松加賀・同兵部の墓所が、今は槍場という所の道を挟んで両方にある)
【当時人々の評価】
この合戦は、朝は立花勢東から西に向かい、宗像勢は西に備えたので、朝日の光がまぶしくて働きが自由にできなかった。夕は立花勢は犬鳴山を背にして東向きに備え、宗像勢は夕日に向かうことになった。立花勢は自然と天の時・地の利に従い、宗像勢は天の時に逆らい、地の利を失った。これは(宗像勢の)戦立ての拙いところであると、人は皆、評したとのことである。
【宗像氏貞が千余人で出陣するも、敗戦を知り引き返す】
宗像氏貞もかかる戦さに及んだことを聞き、千余人を率いて赤間の城を進発したが、味方が打ち負け、敵は早くも撤収したと聞いて、途中から引き返された。これから再び立花と宗像は戦争状態となり、所々での小競り合いは止むことがなかった。
【貝原益軒の評価】
おおよそこの小金原合戦は、宗像家人で西郷から若宮河内に移された三十余人の者どもが、久しく住み慣れた郷里を離れなければならなかったことを恨んだだけが原因である。それも宗像・立花が和睦し、婚姻を結んだうえ、和議によって地を交換したのである。特に君命なのだから、例え我が身にとって良くないことであっても、立花家に恨みをなすべきではない。いわんや旧里を離れただけで領地を失ったわけでもない。どこに恨むべきことがあろうか。かつまた、立花家からあらかじめ人数を通すことの通知もあり、氏貞が了承し、立花家の兵がその地を往来するときはつつがなく通すように下知があったのに、その命令を聞いていながら無視し君命に背いたことは、莫大な罪科である。
次に主人と立花家との和睦を妨げたことは大不忠である。また、罪無き敵味方を多く殺したことは不仁の至りである。これはいたずらに私心を優先して公益を廃したものといえる。いわんや軍法も武略もなく、考えなしに怒りを抱いてにわかに兵を起こし、要害の地に陣を取る多勢の敵に向かって、小勢で逐次に切りかかり、なすことなく所々で討たれ、ついには味方の多勢を亡ぼされ身を失ったことは、「不義を以て兵を起こし、謀拙きを以て敗る」ゆえである。まことに痴愚の至りであり、是非を論ずるにも気にもなれない。
2.古文書から見た「小金原合戦」の書き下しと大意(桑田和明-令和5年3月18日、宮若市文化振興シンポジウム冊子から)
【1】(永禄12《1569》)11月24日
臼杵鑑速・吉弘鑑理・戸次鑑連宛大友宗麟書状「吉弘文書」
河津掃部助事、近年頼宗像氏貞、毎度至西郷、成競望、動従彼堺乱忩、不及是非候、
氏貞忠意於顕然者、如此之悪党厳重討果、向後右郷無異議様、至氏貞、入魂専一候、如御存知、西郷三百十町分之事、先年所々同前定置料所、至各茂、既坪付銘々渡遣候ツ、万一彼郷之内有失念、坪付等雖相調人候、不可及信用候、被得其意、兼々分別肝要候、
《書き下し》
河津掃部助が事、近年宗像氏貞を頼み、毎度西郷に至り、競望を成し、動もすれば彼の堺より乱忩するは、是非に及ばず候。氏貞が忠意顕然たるに於いては、此くの如きの悪党を厳重に討ち果たし、向後は右の郷に異議なき様、氏貞に至し、入魂専一に候う。御存知の如く、西郷三百十町分の事は、先年所々、前と同じく料所を定め置き、各茂に至し、既に坪付を銘々に渡し遣わし候ツ。万一彼郷の内に失念あらば、坪付等を相調うる人候と雖も、信用に及ぶべからず候。其意を得られ、兼々分別、肝要に候。
《大意》
河津掃部助の事です、近年、宗像氏貞を主人と頼むようになり、毎回西郷に至って争いをなし、何かにつけて争乱を起こしています。全く仕様がありません。氏貞が忠義の心をはっきりさせるならば、このような悪党を厳重に討ち果たし、今後は西郷に反対勢力が出ないようにせよと氏貞に伝えるとともに、(氏貞とは)親密であることが何より大事です。
御心得のように、西郷三百十町分は先年から大友が直轄領を定め、各茂(給人)に伝え、既に坪付を銘々に遣わしています。万一、西郷のなかで失念したことがあると、坪付等を調えてくる人があっても、信用することはできません。その意をくんで日頃からよく分別しておくことが重要です。
《解説》
「彼の堺」とある西郷は、大友氏と宗像氏貞に属する河津隆家が支配を争う境目の場であった。大友氏が西郷を支配下に置いたのがいつのことかは不明だが、氏貞麾下の隆家の存在によりその支配は揺らいでいた。
【2】(元亀1年《1570》か)年未詳7月16日
入田鑑実宛大友宗麟預け状「入田文書」
筑前国鞍手郡内若宮庄三百五十町分之事、預進之候、有知行笠木城被取誘、
無緩勤番肝要候、為御存知候、恐々謹言
《書き下し》
筑前国鞍手郡内若宮庄三百五十町分の事、之を預け進じ候、知行を有ちて笠木城を取り誘い、緩みなく勤番すること肝要に候、御存知の為に候、恐々謹言
《大意》 存知=心得 城誘=修築(三重野誠「戦国期における城誘」)
筑前国鞍手郡内若宮庄三百五十町分の事ですが、これをお預けいたします。知行を有ち、笠木城を修築し、緩みなく勤番することが重要です。心得のために述べました。恐々謹言。
《解説》
【1】~【7】の文書の年次は明らかではないが、大友宗麟の花押の形から、すべて永禄12年(1569)から天正3年(1575)発給と思われる。また、戸次鑑連は天正2年(1574)に入道して道雪と号するので、【1】【3】【4】はそれ以前である。
【2】の文書の「若宮庄」は、【1】【3】【5】【6】【7】の文書においては「吉川庄」と呼ばれている。どちらも三百五十町とあるので同じ場所である。おそらく【4】も同様であろう。
【3】(天正1年か《1573》)年未詳4月28日
小田鑑貞宛大友宗麟書状「大坪文書」
吉川庄之事、堅固被申付之由候、尤肝要候、雖無申迄候、毎事無緩覚悟専一候、
殊彼庄之内、鑑連被申事候哉、既以分別申与候上者、即時鑑連江申遣候条、
不可有別儀候、為存知候、恐々謹言
《書き下し》
吉川庄の事、堅固に申付けらるるの由候は、尤も肝要に候。申す迄もなく候と雖も、
毎事緩みなき覚悟専一に候。殊に彼の庄の内は、鑑連、申さるる事候哉。
既に分別を以て申し与え候上は、即時に鑑連へ申し遣わし候条、別儀あるべからず候。
存知の為に候。恐々謹言。
《大意》
吉川庄の事、しっかりと申し付けられたとのことですが、なるほど重要なことです。
申すまでもないことと雖も、何事にも緩みのない覚悟が第一です。
殊に彼の庄の内は、(戸次)鑑連が申されたことがありました。
既に考えて申し与えたうえは、即時に鑑連に申し遣わすことに支障があってはなりません。
心得のために述べました。恐々謹言。
【4】(元亀2か3年《1574か1575》)年未詳12月12日
小田鑑貞宛戸次鑑連書状「大坪文書」
今度別忝被請 上意、至吉川御入部、千秋万歳候、鑑連本望此時候、然者当庄之事、
毎事堅固被仰付、無御油断御裁判専一候、若一雅意之族共候者、鑑貞可被任御存分事、
不可有余儀候、自然御用等之時者、不嫌夜中示給、可得其心候
《書き下し》
今度、別けて忝くも 上意に請われ、吉川御入部に至る。千秋万歳に候。鑑連の本望は此の時に候。然れば当庄の事、毎事、堅固に仰せ付けられ、御油断なき御裁判、専一に候。若し一雅意の族ども候わば、鑑貞が御存分に任さるべき事、余儀有るべからず候。
自然御用等の時は、夜中を嫌わず示し給え。其心を得べく候。
《大意》
このたび、忝くも(宗麟様の)上意に請われて吉川に御入部されることとなりました。まことにめでたいことでございます。鑑連はこのことを待望しておりました。されば、吉川庄のことは何事もしっかりと仰せつけられ、御油断なき政治が大事でございます。もし、わがままをなす者どもがございましたら、鑑貞殿の思うようになされることに別意あるはずがございません。さりながら御用等があるときは、夜中であってもしっかりとお示しになり、その心を得るべきでございます。
【5】年未詳11月25日
小田鑑貞宛大友宗麟書状「大坪文書」
殊一城被取誘之由候。堅固之覚悟、案中候。弥無油断心懸専一候。
《書き下し》
殊に一城を取り誘わらるの由に候。堅固の覚悟、案中に候。弥よ油断なき心懸け専一に候。
《大意》
特に、一城を取り御修築なされたとのことですね。堅固な御覚悟の程、期待通りでございます。いよいよ御油断なき心懸けが大事でございます。
【6】年未詳8月25日
小田大和入道宛大友宗麟書状「大坪文書」
此間所労之由候。能々養生肝要候。仍其方一跡吉川庄三百五十町分之事、右田左近入道息靏房可有相続之由承候条、続目之判形遣候。
《書き下し》
此間、所労の由候。能々の養生、肝要に候。仍て其方の一跡吉川庄三百五十町分の事、右田左近入道の息靏房が相続あるべきの由、承り候条、続目の判形を調え遣わし候。
《大意》
最近病気であるとか。よくよくの養生が大切です。よって貴殿の御領地の吉川庄三百五十町のことですが、右田左近入道の子息靏房が相続すること、承りましたので、相続の印判をととのえて遣わしました。
【7】(年未詳)11月8日 ※小田民部少輔=石田の子、小田の養子
小田民部少輔宛大友宗麟預ケ状「大坪文書」
近年之忠義誠無比類候。仍為其賞筑前国之内吉川庄三百五拾町分之事預置候。
可有知行候。恐々謹言。
《書き下し》
近年の忠義、誠に比類なく候。仍って其賞の為に、筑前国の内吉川庄三百五拾町分之事、預け置き候。知行あるべく候。恐々謹言。
《大意》
近年の忠義は、まことに比類がありません。よってその賞として、筑前国の内の吉川庄三百五拾町を預け置きます。知行するように。恐々謹言。
《解説》
【2】~【7】の文書から、若宮庄(吉川庄)はこの時期大友氏の支配下にあったと考えられ、『宗像追記考』にある氏貞と大友氏の和睦および氏貞妹と道雪の婚礼により若宮庄と西郷が交換されたとの記述も参考にすべきである。
【8】(天正6年《1578》)第一宮御宝殿御棟上之事置札 宗像大社所蔵
一 御領中人夫之事(中略)
一 山口郷、宮永村、稲光村、在木村、室木村、宮田郷、長江津留
《書き下し》
一 御領中人夫の事(中略)
一 山口郷、宮永村、稲光村、在木村、室木村、宮田郷、長江津留
《解説》(若宮町誌上P558より)
宗像氏貞と大友氏の和睦により、氏貞領の住人は束の間の平穏を得ることができた。この間に氏貞は宗像大社辺津宮第一宮本殿造営に取りかかる(この本殿と小早川隆景造営の拝殿は現在重要文化財に指定されている)。
この置札によれば領内は十手に編成され、総勢で四千余人を動員、これを十一巡務めたとある。このうちの一手は、山口郷、宮永村、稲光村、在木村、室木村、宮田郷、長江津留(宮若市内と周辺地域)であった。宗像郡内とくらべ鞍手郡・遠賀郡の負担は、信仰圏の関係から少なかったと考えられるが、和睦後、宗像氏貞の支配がこの地に及んでいたことを示している。
【9】(天正9年《1581》10月15日)鹿子木舜三か宛朽網宗歴書状「鹿子木文書」
其外麻生・宗像以手切致参上、秋月格護之一城笠木岳取破、抽忠儀候、何様両筑之事者、不可入御手候、頓為被仰合、其表御働有無、急度預御入魂、可得其意候、尚期来信候、
恐々謹言
《書き下し》
(前略)其外、麻生・宗像手切を以て参上致し、秋月格護の一城笠木岳を取り破り、
忠儀を抽きんじ候。何様両筑の事は、御手入るべからず候。やがて仰せ合されんが為、
其の表の御働の有無、きっと御入魂に預かり、其の意を得べく候。尚、来信を期し候。 恐々謹言
《大意》
(大友家重臣朽網宗歴が肥後隈本城主鹿子木鎮有?に九州北部の状況を伝えた記述の後)、
その他、麻生・宗像は毛利氏と手切れをして大友方に帰参し、秋月氏が守る笠木城を攻め落として忠義を明らかにしました。まったく筑前・筑後のことは思うようにはなりません。だからすぐにその相談のため、その方面での戦さ働きの有無など、必ず(宗麟の)と親密になり、その心を得ることになるでしょう。お手紙を期待しております。恐々謹言。
《解説》
天正6年(1578)11月、大友宗麟は耳川で島津義久に敗れ、北部九州はまたもや動乱期に入る。氏貞は同年8月17日、戸次道雪の仲介により筑紫広門と相違なき旨を誓約(「宗像神社文書」)、同8年(1580)2月21日、香春岳麓で毛利方の高橋元種と掛け合い(「竹井家文書」)、同9年(1581)10月15日の大友氏家臣朽網宗歴の書状に、麻生・宗像が手切れをもって参上し、秋月方の笠木城を取り破った(「鹿子木家文書」)と記されるなど、表向きには宗像氏貞は大友方として活動しているように見える。
しかし、天正7年2月2日、秋月種実の重臣が氏貞の重臣許斐氏備・占部賢安・吉田重致に起請文を送り、秋月氏が大友氏に背き毛利氏に通じることを伝え、氏貞が同意するなら疎略がないことを誓約している(「宗像神社文書」)。この時代、起請文の案文は相手(すなわち宗像側)によって作られるので(『戦国大名の外交』丸島和洋2013)、宗像氏はこの内容に賛同、少なくとも熟知していたことになる。
また、同年7月3日には龍造寺隆信・鎮賢(政家)親子が氏貞に起請文を送り、今度一意成立したことに両家の間で表裏がないことを誓約している(「宗像神社文書」)。
戦国の世であり、二股三股は武略のうちかも知れないが、和睦後の平和を享受しながらも氏貞の周囲は大友との対戦を控えて慌ただしくなっていく。
【10】天正9年(1581)戸次道雪着到状「立花文書」
(大友義統花押)
天正九年十一月十三日、於山東宗像表合戦之砌、戸次伯耆入道道雪家中之衆、或分捕高名、或被疵戦死之着到令披見訖、
頸一 石松新三郎 米多比新蔵人討之
(中略)
同一 秋月内古閑帯刀 船越兵庫助討之
(以下略)
※ 道雪方の分捕 一六四人、負傷一一八人、戦死一五人
※ 名前が書かれた宗像勢二十四人の内に、河津衆がいる。
深川九郎(河津の子)、晴家次郞(氏澄)・井原次郞左衛門・深川修理
《書き下し》
(大友義統花押)
天正九年十一月十三日、山東宗像表において合戦の時、戸次伯耆入道道雪家中の衆、
或いは分捕高名、或いは被疵・戦死の着到を披見せしめ訖んぬ。
頸一 石松新三郎 米多比新蔵人、これを討つ
(中略)
同一 秋月内古閑帯刀 船越兵庫助、これを討つ
(以下略)
《大意》
天正9年(1581)11月13日、山東の宗像表において合戦の時、戸次伯耆入道道雪家中の衆が、或いは敵の頸を取り、或いは戦傷・戦死したとの着到状を拝読いたしました。
頸一 石松新三郎 米多比新蔵人、これを討つ
(中略)
同一 秋月内古閑帯刀 船越兵庫助、これを討つ
(以下略)
【11】(天正9年)十一月二十四日、吉田島若(貞鎮)宛宗像氏貞感状「吉田ツヤ文書」
於去十三日鞍手郡内吉川庄敵城山下立花衆懸合、遂防戦、父次郞左衛門尉貞辰討死訖、連々覚悟云、本意云、無忠儀比類次第誠感悦之、併累年奉公不異于他之条、別而不便極者也、守先祖之勲功弥可抽馳走、何様不可有忘却候、恐々謹言
《書き下し》
天正9年11月24日、吉田島若(貞鎮)宛、宗像氏貞感状「吉田ツヤ文書」
去る13日、鞍手郡内吉川庄の敵城山下にて立花衆と掛け合い、防戦を遂げ、父次郞左衛門尉貞辰、討死し訖んぬ。つらつら覚悟と云い、本意と云い、忠儀比類なき次第、まことに之に感悦す。併せて累年の奉公、他に異ならざる之条、別して不便(憫)極まる者なり。先祖の勲功を守り、いよいよ馳走抽きんずべく、何様忘却あるべからず候。恐々謹言。
《大意》
天正9年11月24日、吉田島若(貞鎮)宛て、宗像氏貞の感状 「吉田ツヤ文書」
去る13日、鞍手郡内吉川庄の敵城山下において立花衆と掛け合い、防戦を遂げ、父次郞左衛門尉貞辰が討死してしまった。つくづく、覚悟と云い、本意と云い、忠儀比類なき様子に、まことに感悦した。併せて累年の奉公も、だれに異なることなく、特に、気の毒きわまりないことであった。先祖の勲功を守り、いよいよ尽力を卓越するよう、とにもかくにも忘れてはなりません。恐々謹言。
【12】(天正9)11月24日 薦野増時宛戸次道雪・統虎連署感状「薦野文書」
前之十三於清水原合戦之刻、別而被砕御手、深川九郎被討捕御高名之次第珍重候。尖奉達上聞候之条、御感不可有余儀候。殊御被官歴々或分捕、或被疵或尽粉骨候間、是又銘々以状申候。為御為存知候。必以時分顕御志可申候。恐々謹言。
《書き下し》(天正9)11月24日 薦野増時宛て戸次道雪・統虎連署感状「薦野文書」
前(月)の十三(日)、清水原に於ける合戦の刻り、別けて御手を砕かれ、深川九郎を討ちとらるるご高名の次第、珍重に候う。尖奉(先報)、上聞に達し候の条、御感余儀あるべからず候。殊に御被官の歴々、或いは分捕り、或いは疵を被り、或いは粉骨を尽くし候間、是れもまた銘々状を以て申し候。御為と存知る為に候。必ず時分を以て御志を顕す可く申し候。恐々謹言。
《大意》
(天正9)11月24日、薦野増時宛て、戸次道雪・統虎連署感状「薦野文書」
前月(10月)の十三日、清水原における合戦の時、特に様々な工夫を凝らされ、深川九郎を討ちとられたご高名の次第は珍重でした。先報が上聞に達せられ、(宗麟様の)御感は他にないものでした。ことに家来の皆様があるいは相手の首を取り、あるいは疵を被り或いは全力を尽くされたので、これもまた書状でもって申しました。貴方のためと思って行いました。必ず時分が到れば、あなたの御志が顕れるよう申しました。恐々謹言。
【13】(天正10)4月26日 小早川隆景宛宗像氏貞書状写「無尽集」
去年11月12日至毛利鎮真要害高鳥広、戸次道雪、兵粮差籠候条、翌日十三待請於吉川庄、敵切寄山下数箇度遂防戦、悴者以下尽粉骨候。勿論敵数輩討果、手負不知其数候。家頼之者共、是又手負・討死数十人、誠砕手候。同十四日許斐岳取付、人数差籠候処、愚領分宮地岳従立花城取候間、即時ニ田嶋・宮永両口二向城銘々申付、至今日。鉾楯無寸暇候。仁保隆慰迄遂注進候ツ。於干今者不及申候。宝満・立花相詰候。山道故、無気遣往返候。
両家之襲以一家之力可申付事、気遣仕候。
《書き下し》(天正10)4月26日 小早川隆景宛て、宗像氏貞書状写「無尽集」
去年11月12日、毛利鎮真の要害高鳥広に至り、戸次道雪、兵粮を差し籠め候条、翌日十三日に吉川庄に待ちうけ、敵の切寄山下に数箇度防戦を遂ぐ。悴者(かせもの)以下粉骨を尽くし候。勿論敵数輩を討ち果たし、手負その数を知らず候。家頼(けらい)の者ども、是れまた手負い・討死数十人、誠に手を砕かれ候。同十四日、許斐岳に取り付き、人数を差し籠め候処、愚領分の宮地岳、立花城より取り候間、即時ニ田嶋・宮永両口に向城を銘々申し付け、今日に至る。鉾楯、寸暇なく候。仁保隆慰まで注進を遂げ候ツ。ここにおいて今は申すに及ばず候。宝満・立花相詰め候。山道あるが故、気遣いなく往返し候。両家の襲、一家之力を以て申し付くべき事、気遣い仕り候。(後略)
《大意》(天正10)4月26日 小早川隆景宛て、宗像氏貞書状写「無尽集」
去年11月12日、毛利鎮真の要害高鳥広に至り、戸次道雪が兵粮を差し籠めましたこと
についてですが、翌日十三日に吉川庄に待ちうけて、敵城の山下(稲光城)で数箇度防戦を遂げました。悴者(かせもの=武士身分ではない家来)以下粉骨を尽くしました。勿論敵数輩を討ち果たし、手負いはその数がわかりません。家頼(けらい)の者どもは、是れまた手負い・討死数十人、誠に全力を尽くしました。同十四日、許斐岳を始めとして人数を差し籠めましたところ、私の領分の宮地岳を、立花城から攻め取られましたので、即時に田嶋・宮永両口に向城を銘々申し付け、今日に至っています。戦いが少しの休みもなく続いております。(毛利家来の)仁保隆慰まで報告をしております。今ここで申し述べることができないほどです。宝満・立花に取り囲まれております。しかし、山道がありますので、通行に支障はありません。両家(高橋・立花)の襲撃を、(宗像)一家だけの力で防ぐよう命じられることは、不面目なことになりそうで心配です。(後略)
《解説》
この書状は宗像氏貞が小早川隆景に対し、九州の状況を報告し、あわせて宗像及び九州方面に対する毛利の心入れを要請したものである。長文なので要旨を列挙して、宗像氏貞から見た当時の北九州の状況を概観したい(北九州戦国史史料集下:八木田謙P666から)。
① 天正9年11月12日大友方鞍手郡鷹取城将毛利鎮真の兵粮援助のため、立花山城の
戸次道雪、鷹取城に兵粮を入れ、帰り道に宗像勢と11月13日、吉川庄において合戦、14日、その余勢を以て立花勢、宗像領宮地岳を占領する。その旨を門司城番仁保隆慰に注進した。
② 天正9年冬、秋月種真・龍造寺隆信・筑紫広門が日田口(針目城か)を差しおさえた。
大友勢の日田郡における兵力は少ない。
③ 馬ヶ岳の長野と香春の高橋元種は、天正9年10月の長野の松山城攻め以来の不和で、秋月と長野も不仲により、10年3月下旬、秋月・高橋(毛利方)が、ともに長野(毛利方)の馬ヶ岳城を攻める。鷹取の毛利鎮真(大友方)は落去して長野領分に居り、城井鎮房(毛利方)・岩石城の坂本永泉(大友方)も、長野に味方して馬ヶ岳城の防戦で勝利を挙げる。このように毛利の味方同士が友食いして、毛利家のお役に立たない状態である。
宇佐郡妙見岳に田原紹忍が居り、味方する者が少しばかりいる。
④ 島津勢は、策略により宇土・相良城の赤星を引き取らせ、(島津勢が)阿蘇に攻め込んだ。阿蘇の甲斐宗運は、天正9年12月2日、下益城郡豊野村贄原において島津方の相良義陽父子を討ち取ったが、その相良跡を薩衆勢が乗っ取ったので、肥後国中が動揺し残りの肥後衆は龍造寺に一味した。
⑤ 天正10年3月15日、立花・宝満領内の麦薙ぎを、秋月・筑紫・龍造寺勢で行い、引き続き立花山城に攻め込むことを竜造寺に勧めたが、肥後口出張のため延引している。時機を失すると敵を討ち漏らすので、毛利方から龍造寺に仰せ下されたい。
⑥ 島津勢と龍造寺勢が合戦になれば、大友勢は漁夫の利を得るので、秋月とともに心配している。そうなれば、宝満・立花は休息できる。立花・宝満は大友家の武力の根源で、我ら毛利一味はそのことが心配である。
⑦ 中国筋の対策は、如何、委細お知らせ下されたく、御手塞がり故遠国の宗像にはご配慮いただけないことは残念、当方も貴意を得られず残念、その点御理解願いたい。吉左右をお待ちしている。
【14】『宗像記追考』
※ 若宮庄友池・金丸に西郷より移りし三十六人の給人
※ 十三日の午の刻、立花勢、鷹取より帰る処に、杉十郎は秋月の一味なれば、龍徳より人数を出して、食い止めんとす。立花勢、忽ちに責め崩し、城下まで追い詰め、静々と帰りけるが、友池川に来て(以下略)
※ 立花勢、友池を打ち破り、原田を指して引き取る処を、友池・金丸の人々、跡を慕って付けければ、(中略)金生の前の川を渡って、高野を指して引き取りけるに、若宮所々の住人、遅れ馳せに駆け付くるを、或いは追い払い、或いは打ち取り、ひた引きに引きて稲光の城山に取り上り、勢をまとめて、人馬の息を休めけり。若宮の人々も、小伏の前まで追いかけ、ここにて人馬を休めけり。
※ (宗像氏貞より制止を命じられた吉田貞辰・石松秀兼は)原田・金生を打ち過ぎ、下村の川を渡り、小金原に打ち出る。友池・金丸の人々は、小伏の前の野にはせ集まり、人馬を休め、軍の評定をする処に、吉田・石松はせ着く。
※ (吉田・石松も合力)友池・金丸・長江津留、その他若宮庄にあらゆる侍等、雑兵ともに二百余人、また赤間より馳せ来たる吉田・石松に聞きがけに追いつく人々には(中略)彼是人数百余人、都合三百人ばかり、小伏の前に備えを立て、城山の敵にかからんとす。
《大意》
※ 若宮庄友池・金丸に、西郷から移り住んだ三十六人の給人(武士)
※ 十三日の午の刻(十二時頃)、立花勢が鷹取から帰るときに、杉十郎(連緒)は秋月の味方だったので、龍徳城から兵を出し、立花勢を食い止めようとした。立花勢は、ただちに杉勢を攻め崩し、城下まで追い詰め静々と帰ってきていたが、友池川に来て(以下略)
※ 立花勢は、友池を打ち破り、原田を指して引き返すところを、友池・金丸の人々は、立花勢を追跡したので、(中略)金生の前の川を渡り、高野を指して引きとっていたが、若宮所々の住人が、遅れ馳せに駆け付けたのを、あるいは追い払い、あるいは打ち取り、一直線に退いて稲光の城山に取り登り、勢をまとめて、人馬の息を休めた。若宮の人々も、小伏の前まで追いかけ、ここで人馬を休めた。
※ (宗像氏貞より制止を命じられた吉田貞辰・石松秀兼は)原田・金生を過ぎ、下村の川を渡り、小金原に達した。おりしも、友池・金丸の人々が小伏の前の野にはせ集まり、人馬を休めながら、軍の評定をしていたところに、吉田・石松勢が到着した。
※ (吉田・石松も合力)友池・金丸・長江津留、その他若宮庄のあらゆる侍たちが雑兵合わせて二百余人、また赤間から来た吉田・石松の触れを聞いて駆けつけ追いついた人々には(中略)かれこれの人数百余人、合計三百人ばかりが小伏の前に備えを立て、城山の敵にかかろうとした。
【15】『河津伝記』
※ 秋月家臣江利内蔵助、穂波郡笠木の城を守りけるが、三百余人を卒し、小金原に出て加勢しける。
《大意》
秋月家臣江利内蔵助は、穂波郡笠木の城を守っていたが、三百余人を率い、小金原に出て加勢した。
【16】『豊前覚書』
※ 十二日之晩より麓を打立、十二日之夜中に高鳥麓、永満寺へ持入、森(了信)殿へ渡被申候、然は、宗像衆・麻生甚五衆・秋月衆関所之中を切通、御籠被成候、夕部は右之衆無難通、立花衆引申所を不残打果可申談合仕、夕部人数豊前被罷通候時、甚五衆物隠より(中略)金原・清水原所々に而、火を出候、鑓撞被申候、秋月・宗像之人数悉追打被仕。
《書き下し》
※ 十二日の晩より麓を打ち立ち、十二日の夜中に高鳥の麓、永満寺へ持ち入り、森(了信)殿へ渡し申され候。然れば、宗像衆・麻生甚五衆・秋月衆、関所の中を切り通り、御籠り成され候。夕部は右の衆、難なく通る。立花衆、引き申すところを残らず打ち果たす申すべく談合仕まつる。夕部の人数は、豊前罷り通され候時、甚五衆、物隠より(中略)金原・清水原所々にて、火を出し候。鑓を撞き申され候。秋月・宗像の人数、悉く追い打ち仕まつらる。
《大意》
※ 十二日の晩より麓を打ち立ち、十二日の夜中に鷹取の麓の永満寺へ兵粮を持ち入れ、毛利(了信)殿へ渡されました。それで、宗像衆・麻生甚五衆・秋月衆は、関所の中を切り通り、御籠り成されました。夕部は右の衆は難なく通りました。立花衆が引くところを、残らず打ち果たそうと談合いたしました。夕部の人数は、豊前が罷り通った時、甚五衆が物隠から(中略)金原・清水原の所々にて、火をかけられました。鑓を撞かれました。秋月・宗像の軍勢は、悉く追い打ちいたされました。



コメント