 村別 福岡県地理全誌
村別 福岡県地理全誌 34 香月村
日本武尊の部将「小狭田彦」に始まり、山鹿兵藤次秀遠の一族、浄土宗二世鎮西国師聖光の宗家として、長く遠賀郡に力を及ぼした香月一族の中心地香月村。数々の伝承がこの村を飾ります。
 村別 福岡県地理全誌
村別 福岡県地理全誌 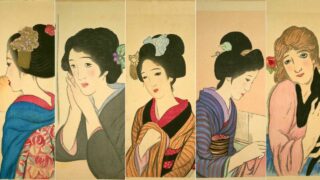 八幡製鉄所記事
八幡製鉄所記事  TOPICS記事
TOPICS記事  村別 福岡県地理全誌
村別 福岡県地理全誌  村別 福岡県地理全誌
村別 福岡県地理全誌  村別 福岡県地理全誌
村別 福岡県地理全誌  村別 福岡県地理全誌
村別 福岡県地理全誌  鎌倉記事
鎌倉記事 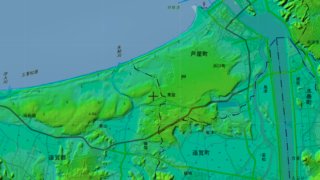 村別 福岡県地理全誌
村別 福岡県地理全誌  村別 福岡県地理全誌
村別 福岡県地理全誌  鎌倉記事
鎌倉記事  村別 福岡県地理全誌
村別 福岡県地理全誌  村別 福岡県地理全誌
村別 福岡県地理全誌  遠賀郡 福岡県地理全誌
遠賀郡 福岡県地理全誌  TOPICS記事
TOPICS記事  TOPICS記事
TOPICS記事  鎌倉記事
鎌倉記事  TOPICS記事
TOPICS記事 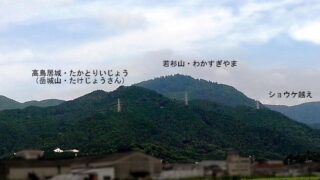 TOPICS記事
TOPICS記事  TOPICS記事
TOPICS記事 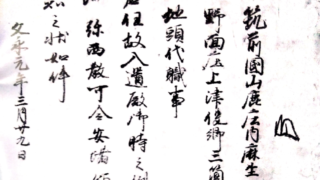 鎌倉記事
鎌倉記事  鎌倉記事
鎌倉記事  鎌倉記事
鎌倉記事  鎌倉記事
鎌倉記事  鎌倉記事
鎌倉記事  鎌倉記事
鎌倉記事 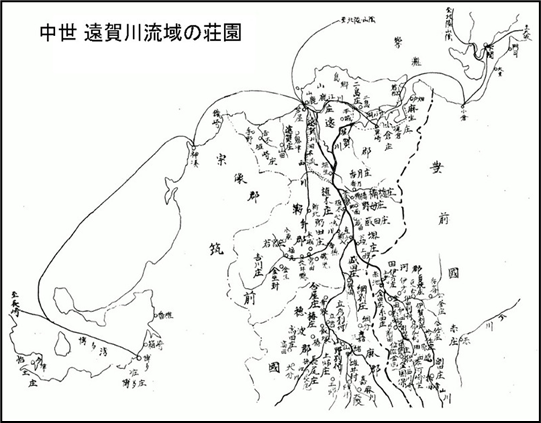 鎌倉記事
鎌倉記事  鎌倉記事
鎌倉記事  鎌倉
鎌倉  TOPICS記事
TOPICS記事